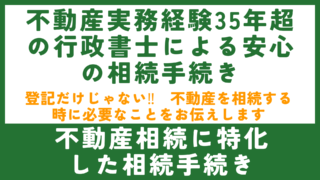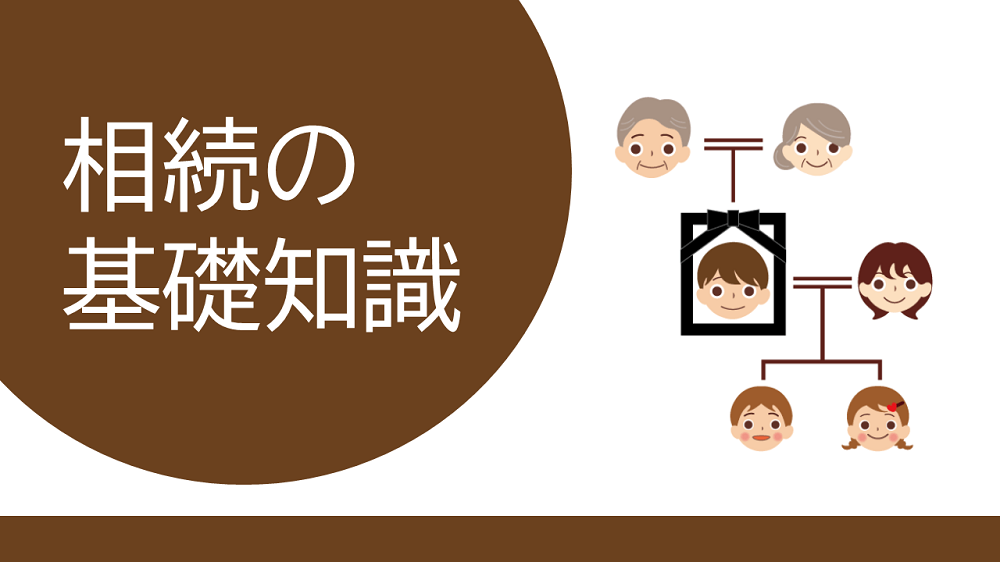遺言書では「○○を法定相続人Aに相続させる」という記載が一般的ですが、「●●へ遺贈する」という記載があった場合はどうしたらいいでしょうか。近年では福祉系の団体へ遺贈する方も増えています。ここでは遺贈の手続をご案内します。
遺贈とは
遺言によって特定の財産や財産の割合を指定して、特定の者(相続人以外や法人・団体でも可能)へ財産を引き継がせることができます。遺贈する人を遺贈者、遺贈される人や団体を受遺者といいます。民法891条に規定される相続人の欠格事由に該当する場合は、受遺者としての地位も失います。また、胎児は受遺者になることができます。
生前贈与では、あげる側ともらう側の合意が必要ですが、遺贈では遺贈者の意思表示(遺言)だけで成立します。受け取りたくないという受遺者は遺贈を放棄することができます。詳しくは後述する遺贈の放棄欄をご覧ください。
遺言通り権利承継の手続きをする人
遺言書に遺言執行者が指定されているときは、遺言執行者が遺贈の手続きを行います。指定されていない場合は家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てるか法定相続人が遺贈義務者として手続きを行います。
遺贈の種類
特定遺贈
特定遺贈は、遺贈の目的財産を特定して行う遺贈です。
例)A不動産を友人Bに遺贈する
C会社の株式1000株のうち500株を友人Dへ遺贈する
E銀行の普通預金の60%を友人Fへ遺贈する
包括遺贈
包括遺贈とは、財産を特定せず、割合で遺贈するものです。全財産を遺贈する包括遺贈の場合は遺言執行者が権利承継の手続きを行います。
例)全財産をA団体に遺贈する
遺産のうち3分の1をB団体に遺贈する
負担付遺贈
負担付遺贈とは、受遺者が一定の行為をすることを条件にした遺贈です。
例)A銀行の預金のうち1000万円を息子の嫁であるBへ遺贈する。
ただし、Bは自分の妻Cが存命中は、一切の面倒をみなければならない。
清算型遺贈
遺贈の方法として遺産を売約してその代金を遺贈する方法があり、これを清算型遺贈といい不動産や株式でよく使われます。清算型遺贈であった場合は遺言執行者が財産の売却を行うことができますので、不動産を売却するための登記申請や媒介契約、売買契約なども遺言執行者が単独で行うことができます。なお、不動産を売却するとき、亡くなった登記名義人から新たに購入する人へ直接所有権移転登記ができないため、最初に法定相続人名義で遺言執行者が登記申請を行います。その後に買主へ所有権移転登記を行います。
種類別の遺贈の効果
特定遺贈による権利承継
特定遺贈の場合、遺言執行者や相続人が遺贈義務者として引渡しや所有権移転登記を行ったときに遺贈が完了します。包括遺贈のような特定遺贈された財産以外の負債を相続することはありません。
包括遺贈による権利義務承継
包括遺贈による受遺者(包括受遺者といいます)は相続人と同一の権利義務を有します(民法990条)。そのため相続が発生したと同時に、権利だけでなく義務を含めて受遺者に移転します。
<包括遺贈の注意点> ①負債も引き継がれる 包括遺贈ではプラスの財産だけでなく受贈された割合に応じて負債も引き継がれます。被相続人の経済状態をよく知る子供の配偶者や孫など身内への遺贈ならまだしも、お世話になった知人、福祉団体などの第三者の方は注意が必要です。実際に包括遺贈では受贈しないと定めている団体が多いようです。 ③遺産分割協議に参加する場合もある 全部の包括遺贈を受けた場合または清算型包括遺贈により全財産を現金化して割合で分ける場合は法定相続人と遺産分割協議を行う必要はありませんが、割合で包括遺贈を受けた場合は分割する財産を特定するため相続人と一緒に遺産分割協議を行う必要がでてきます。そのため、時間がかかったりトラブルに巻き込まれたりすることも考えられます。
負担付遺贈の場合の権利義務
負担付遺贈の場合、遺贈された財産価額を限度として、条件とされた負担を履行する責任を負います。ただし遺贈された遺産以上の責任を負うことはありません(民法1002条1項)。
遺贈の放棄
遺贈の放棄は遺贈の種類によって手続きが違います。なお、一度承認又は放棄の意思表示をしたら撤回はできません。
特定遺贈の放棄
特定遺贈の受遺者は、遺贈者の死亡後はいつでも遺贈の放棄ができます(相続発生前に放棄はできません)。特定遺贈の放棄は、遺言執行者(いない場合は相続人である遺贈義務者)に対して意思表示を行うだけでよく、一般的には内容証明郵便で行います。放棄した場合は死亡時にさかのぼって効力が生じます。なお特定の財産だけ(遺贈財産は現金と不動産だが現金だけ受け取るなど)、一分の財産だけ(遺贈財産の現金1000万円のうち800万円だけ受け取るなど)放棄も可能です。
受遺者の意思表示がない場合は相続財産の移転がいつまでも確定しない場合があります。そのため相続人は受遺者に対し相当の期間を定め、遺贈の承認又は放棄の意思を求めることができます。受遺者が期間内に意思表示しないときは遺贈を承認したとみなします。
包括遺贈の放棄
包括遺贈を放棄する場合は、相続放棄と同様に、相続が発生して自分に包括遺贈があったことを知ったときから3ケ月以内に故人の最終住所地を管轄する家庭裁判所に遺贈の放棄の申述を行います。
負担付遺贈の放棄
受遺者が遺贈の放棄をした場合、負担の利益を受ける者は、自ら受遺者となり遺贈を受けることができます(遺言の中にこれと違うことが書かれていた場合はそれに従います)。
遺贈の無効と取消し
受遺者の死亡
遺言者の死亡前に受遺者が死亡したときは遺言の効力が生じません。相続人のような代襲制度はありません。
遺贈の目的物が相続財産に属していない場合
遺贈の目的物が遺言者の死亡時に相続財産ではなかった場合、遺言の効力は生じません。
負担付遺贈の遺言の取消し
負担付遺贈の受遺者がその義務を履行しない場合、相続人の手続きによって遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができます。
遺贈に関する税金
受遺者(個人)にかかる税金は相続税
受遺者は、相続した財産に対して相続税がかかり、通常の相続税の計算方法で計算しますが、下記の点は注意してください。
※受遺者は基礎控除計算の法定相続人の人数には入りません。
※法定相続人以外は、相続税額が2割加算されます。
※死亡退職金や死亡保険金を法定相続人以外が遺贈で受け取る場合は非課税枠は使えません。
法人に対する遺贈は「みなし譲渡所得税」
個人間の遺贈であれば相続税で譲渡所得を考える必要はありませんが、法人に無償譲渡(遺贈、死因贈与、贈与)したときは、遺贈者である個人が所有していたときの値上がり益に対して所得税がかかります。これをみなし譲渡課税といい、被相続人(遺贈者)の準確定申告で譲渡所得税の申告をする必要があります。
納税については、特定遺贈の場合は相続人が承継するため受遺者には申告や納税の義務は発生しません(財産はもらえないのに納税義務だけはあるためトラブルになります)。包括遺贈の場合、包括受遺者は被相続人(遺贈者)の債務を承継するので納税の義務も承継します。
不動産の譲渡所得税は高額になりますので、一つ間違えれば大きなトラブルになります。遺言執行者は税理士に相談して、事前に税務署や相続人・受遺者と打ち合わせを行っておく必要があります。
法定相続人以外の人が不動産を遺贈された場合
特定の不動産を法定相続人以外が遺贈によって取得した場合、不動産取得税がかかります。また法定相続人以外の者が受贈者である場合、相続登記に適用される不動産の登記をするときにかかる登録免許税率の軽減は使えません。
清算型遺贈の譲渡所得税
不動産を対象として清算型遺贈を行った場合、一旦法定相続人に名目上登記され売却されますが、譲渡所得税は1円ももらえない登記名義人である相続人に課税されるのか、それとも受遺者なのかという問題が発生します。譲渡所得税が発生した場合、住民税や国民健康保険料への影響も生じます。これについては国税庁でもはっきりと判断していませんが、受遺者に課税されるというのが主流の考え方のようです(国税庁の公式見解ではありませんので都度税務署に確認しながら進めてください)。
実務では、遺言執行者は税理士に相談し、税務署と事前打ち合わせをして受遺者の申告と納税まで管理します。1円も貰えない相続人に登記名義人だからと納税手続きの通知が税務署から届けばトラブルになることは間違いありません。細心の注意が必要です。